ブラジリアン柔術は練習すればするほど、上達する競技です。
練習は欠かせませんが、自分で研究することも同じぐらい大切です。
本項では、元プロ格闘家が柔術を独学する方法を解説します。
「もっとうまくなりたい」「なかなかジムに行けないけど、上達したい」という方は必見です。
筆者の場合は、柔術の練習は週2回+ウエイトトレーニングを週2,3回やっています。
決して練習量が多いわけではありませんが、柔術を独学するようになってから上達するスピードが早くなりました。
柔術においては、独学は必要不可欠です。
本稿では、
- 柔術が独学で強くなれる理由
- 独学で強くなる方法
以上2点を解説しています。
独学におすすめの著書は【大賀式柔術上達論 見えない構造を解き明かす/大賀幹夫】です。
こちらの書籍は、柔術で効率的に体の使い方が数多く解説されています。
「もっと柔術が上達したい」という方は一読してみるといいでしょう。
柔術家にとっての大辞典!
筆者も愛読!
ブラジリアン柔術に独学が必要な理由

柔術は、ロジカルな思考が必要な競技だからです。
寝技というのは、技に対して正確な対応することが求められます。
正しく技に対応できれば、技は掛かりません。
反対に知らなければ、やられ放題です。
技に対応する方法は、ジムで指導員や先輩に技を教えてもらえます。
しかし、人から教えられたものを覚えていられるでしょうか?
本当に覚えようと思ったら、自らの課題を抽出し、解決しようと思わなければ、人は覚えられません。
- 自分はなぜやられるのか?
- どうしたら相手にやられないか?
ここを考えて、自分なりの答えを導き出せる方は、上達も早いでしょう。
 ふじ
ふじただし、柔術を始めたばかりの初心者の方は例外です
どんなことも基礎ができてないと、学習できません。
ブラジリアン柔術を始めたばかりの白帯の方は、ジムの練習に参加し基礎をしっかり身につけるようにしましょう。
独学で上達する方法


ブラジリアン柔術を独学で上達する方法は3つあります。
上から順番に解説していきます。
その日の練習を振り返る
「スパーリングでどうして一本を取られたのか」と仮説をたて「どうしたら次はやられないのか」対策を練ることが重要です。
この時、たとえ仮説が間違えていても構いません。
大切なのは、自分で仮説をたてることです。
柔術は【体を使ったチェス】と呼ばれるほど、頭を使う競技です。
日頃から自分で考える癖をつけておくことで、上達スピードが一気に早くなります。
スパーリングに参加→自分でやられた原因を考える→対策を練る→スパーリングに参加する→
上記の過程を繰り返していくことで、技に対する正しい知識が身に付いてきます。



スパーでやられた原因を考え、対策を練っていくうちに段々とやられなくなってきました
動画や本で学習する
インターネットが発達した昨今、さまざま技術を取り入れることが可能になってきました。
YouTubeで「柔術」と検索すれば、たくさんのテクニック動画があります。
例えば「ラッソーガード」と調べるだけでも、数多くの動画が閲覧でき、有名な柔術家がその技術を惜しみなく解説しています。
柔術初心者こそ、ラッソーガード!ラッソーのポイントとスイープするコツを解説!
動画は通勤や通学中にもスマホから見られるので、いつでもどこでも学習できるメリットがあります。



書籍で学習する方法もおすすめです
本は動画と違い、以下のようなメリットがあります。
- 写真を使って解説されているので、細かいところまでじっくり観察ことができる
- 情報がまとまっているので、調べやすい
下記の書籍は、画像や文章でテクニックが解説されています。QRコードもあるので、動画でも確認できます。
筋トレを行う


柔術は格闘技なので、体力や筋力は必要です
どんな優れた技術を持っていても、体力や筋力の強さに差があれば技は掛かりません。



一体どんなトレーニングをしたらいいの?



以下の4種目がおすすめです
- ベンチプレス
- 懸垂
- デッドリフト
- スクワット
詳しいやり方は、こちらの記事で解説しています。
【最強への道】柔術家に筋トレは必要!絶対に取り組むべき筋トレメニューとは?
また、筋トレ効果を高めるには、栄養バランスのとれた食事が欠かせません!
米や麺類などの炭水化物、肉や魚などのタンパク質、野菜などのビタミンをバランスよく取るようにしましょう。
とくにタンパク質は不足しやすので、意識して摂るようにしましょう!一般的に体重×2倍のタンパク質が必要と言われています。



食事で摂ろうとすると、ざっとこれぐらいの量が必要です
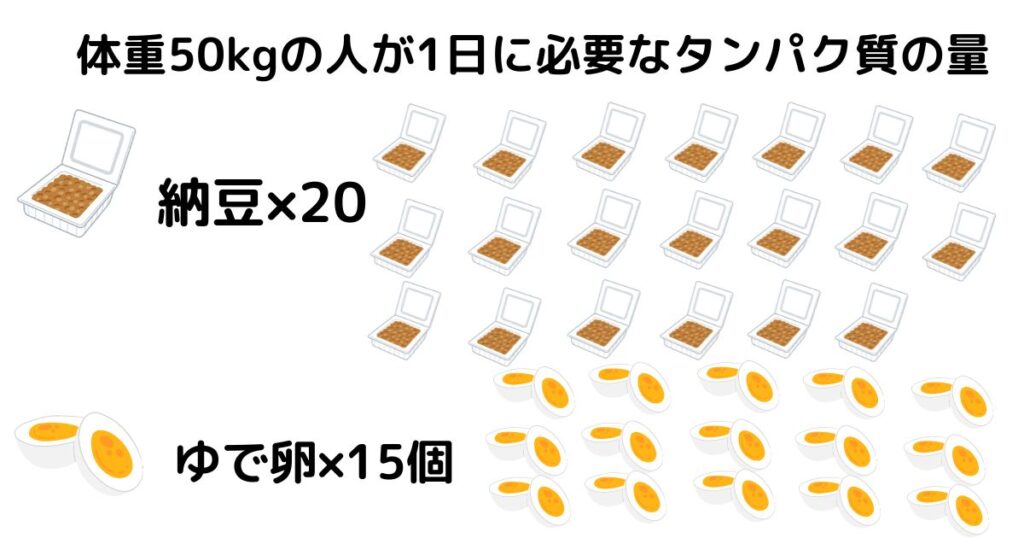
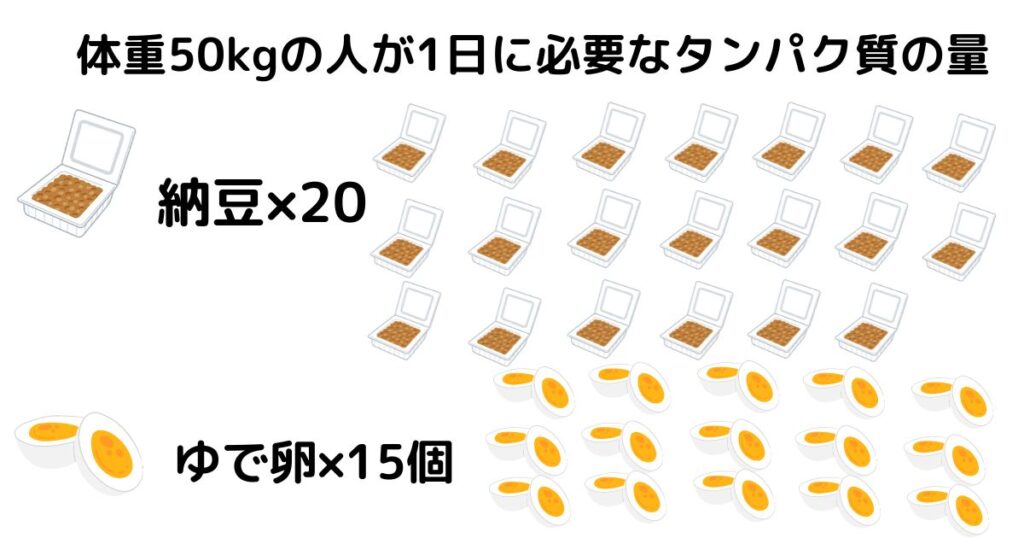



こんな量、絶対に食べきれないよ…



そんな方はプロテインを活用しましょう
おすすめのプロテインは「パーフェクトパンププロテイン」です。
タンパク質だけでなくクレアチニンやBCAAなど、体作りに欠かせない成分が含まれています。



飲み始めてから、周りから一回り体が大きくなったと言われます
公式サイトから購入で、今だけ20%オフ!
筆者も愛用!
独学で強くなれる理由と3つのポイント:まとめ


ブラジリアン柔術を独学で上達する方法を紹介してきました。
独学で強くなることは十分可能です。
筆者の練習頻度は、週に2回と決して多い方ではありません。
それでも自分で技を研究することで、上達してきたと実感しています。



トライ&エラーの繰り返し!それが柔術が上達する道です!
柔術に求められるのは、技に対して正確な対応ができるロジカルな思考です。
本項を参考にして、柔術をさらに上達していきましょう!








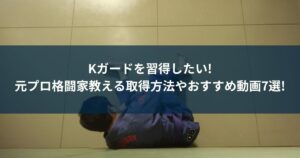




コメント