柔術は「体を使ったチェス」と呼ばれるほど、ロジカルな競技です。
「怪我をしにくい」というイメージもあるようですが、実際はどうなのでしょうか?
本項では、元プロ格闘家で柔術紫帯の筆者が「柔術は怪我をしにくい格闘技」なのか解説します。
 ふじ
ふじぶっちゃけ、余裕で怪我します!
筆者もこれまで、首、腰、指…と様々なところを怪我してきました。
しかし、趣味のブラジリアン柔術で怪我ばかりしていては、続けていくのも容易ではありません。
そこで、本項では柔術で怪我をしやすい箇所と、怪我を予防する方法を紹介していきます。
これを読めば、怪我予防して楽しい柔術ライフが送れることでしょう!
柔術は怪我が少ない競技なのか?


柔術は怪我の少ない競技だと思います。
MMAやレスリングに比べると、怪我のリスクは低く、安全性が高い競技です。



MMAやレスリングの練習では、しょっちゅう怪我をしていましたが…
空手やキックボクシングのように打撃もないので、脳へのダメージも少ないのも安心です。
柔術は寝技中心の非常にロジカルな競技。
怪我予防にきちんと努めれば、大きな怪我に繋がる可能性はぐっと下げられます。



でもやっぱり、怪我をするときは怪我します



どんな怪我が多いの?



どんな怪我が多いのか、詳しく解説していきます
柔術で多い怪我とは


柔術で多い怪我とは、どんな怪我なのでしょうか?
柔術仲間が実際に負った怪我や、筆者が柔術により負傷した怪我を紹介します。
それぞれ詳しく解説していきます。
顔…擦り傷
相手の道着や畳やマットに擦れて、おでこや頬赤い擦り傷ができてしまいます。



寝技がメインの競技なので、顔が擦れてしまうことは仕方ない!
ちなみに縫うほど大きな怪我をしたことはありません。
レスリングでは額や眉間が切れて、縫ったという話はよく聞きました。



キックボクシングなどの打撃系では、顔にアザができる…
柔術やレスリングに比べれば、柔術は大人しい競技です。
首…捻挫
首も柔術で怪我しやすい部位です。
首は相手とのポジションを奪い合うスクランブルや、ブリッジをしてエスケープをしようとときに、首を負傷するケースがほとんどでした。
酷い方だと首の骨が変形し、手が痺れてしまった方もいます…。
首の怪我が一番、怖い…。
指…捻挫、脱臼
道着を掴んで攻防を行う競技のため、指を怪我しやすいと言えるでしょう。
筆者も指を捻挫をしたことは、何回もあります。
ただ指の捻挫なら、湿布を貼って、固定しておけば数日で良くなります。
(怪我をしている間は、指が少し曲がりづらい不便さはありますが…)
腰…ぎっくり腰
急性腰痛症、ぞくに言う「ぎっくり腰」。
柔術は普段、取らないような体制で動くため、腰に掛かる負担もかなりのものです。
「ぎっくり腰」をしたあとは、起きていても、寝ていても激痛で寝返りも打てないほどでした…。
当然、仕事に支障をきたしました…。痛み自体は1週間もすれば回復しましたが、当時の職場にはご迷惑をおかけしました。
しかし腰痛は、どんな職業や競技でも発生するリスクがあります。
一概に「柔術=腰を痛めやすい競技」とは言えないでしょう。
膝…打撲、捻挫
膝でもっとも多い怪我は、膝を床にぶつけたり、捻ったりして打撲や捻挫をするケースです。
筆者も過去に膝を痛めたことがありましたが、タックルやパスをした際に、膝を床に打ってしまい、怪我をしました。
また、柔道やレスリングなどの経験者にありがちなのが、半月板の損傷。
半月は膝関節の大腿骨と脛骨の間にあるC型をした軟骨様の板で内側・外側にそれぞれがあり、クッションとスタビライザーの役割をはたしています。これが損傷すると、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなる“ロッキング”という状態になり、歩けなくなるほど痛くなります。
膝は怪我をすると歩行に支障が出るなど、日常生活に大きな支障をきたします。
膝の怪我については、サポーターを着用するなど、膝を保護すればある程度は予防できます。
ただ試合では着用が認められていないので、サポーターありきの動きに慣れてしまわないように注意しましょう。
足首…捻挫
スタンドの攻防や、パスを狙ったときに足を捻ってしまうパターンが多いようです。
しかし柔道やレスリングのような、立ち技がメインの競技の方が、足首の負傷は多いように感じます。
うーん、でも怪我はするね…
予防をすることは、十分可能です!
怪我をしないためには


怪我をするリスクを下げ、楽しい柔術ライフを送るには何をすべきでしょうか?
怪我予防する6つの方法を紹介していきます。
休憩を取りながら練習する
大半の方は、趣味で柔術をしている方がほとんどでしょう。
趣味で柔術を行っている以上、自分のキャパシティー以上の無理な練習は禁物です。
- 疲れたら休憩をはさむ
- こまめな水分補給をする
- サプリメントを活用する
など練習中のコンディションには、気を使うようにしましょう。
サプリメントって、何を飲めばいいかわからないよ?
サプリメントといっても、様々なものがあります。
練習中のコンディションを維持するには、BCAAやアルギニンがおすすめです。
BCAAはバリン、ロイシン、イソロイシンというアミノ酸の総称で、分岐鎖アミノ酸とも呼ばれます。 運動時の筋肉のエネルギー源となり、運動パフォーマンスを向上させたり筋肉疲労を軽減させたりするはたらきがあります。 そのためスポーツや運動を積極的に行っている方にとって、特に意識して摂りたい栄養素の一つです。
引用:Media Plette
アルギニンは成長ホルモンの分泌を促す働きがあります。 脳下垂体から分泌される成長ホルモンは病気にかかりにくい体を作ったり、傷の治りをスムーズにしたりする効果が期待されています。 また成長ホルモンには食欲を抑える働きがあると考えられ、食欲抑制剤にもアルギニンが加えられています。
引用:glico
しかし「いくつもサプリメントを持ち運ぶのは面倒くさい」という方もいるでしょう。
そんな方には【パーフェクトパンププロテイン】がおすすめです。
【パーフェクトパンププロテイン】には、プロテインだけでなく、BCAAやアルギニンなどが含まれています。
「パフォーマンスアップをしたい」「コンディションを維持したい」方には、おすすめのサプリメントと言えるでしょう。
今だけ公式サイトで購入した方限定で最大20%オフで購入できます。
早めのタップをする
関節技や締め技が入ったら、すぐにタップするようにしましょう。
技を掛けられて悔しい気持ちは分かりますが、関節技や締め技は簡単に怪我します。



技をかけられて我慢していると、思っているより簡単に怪我をします…
取り返しのつかない怪我をする前に、早めにタップするようにしましょう。
それよりも「どうやったら技を掛けられないのか」を考えることが大切です
柔術を始めたい方へ!元プロ格闘家が柔術が向いている人の特徴2選!その内容とは…?



それには柔術をよく理解することです
本や動画などを活用し「技をかけるには、どんなロジックがあるのか」知ることが大切です。
アップやクールダウンをする
練習の前にはしっかりと体をアップさせることも重要です。
身体が温まっていない間に動くのは怪我の元です。



筆者の経験上、体が十分に温まっていないときに怪我をしていました…
遅れて練習に参加するときは、マット運動やストレッチなどで、しっかり体をほぐしてから参加するようにしましょう。
また練習後には、ストレッチでクールダウンをしましょう。
練習後は体に披露が蓄積しています。
疲労が蓄積し続けると、怪我を誘発する原因にもなります。



特に太腿や腰まわりなどは、ストレッチをよくやるようにしましょう
筋トレをする
筋トレはフィジカルを強くするだけでなく、怪我予防にも有効です。
柔術のスパーリングだけでも筋肉は身に付きますが、使う筋肉が偏ってしまい、身体のバランスが崩れてしまいます。



特に太腿や腰まわりなどは、ストレッチをよくやるようにしましょう
筋肉がつくことで、身体にかかる負担が軽減できます。
筋トレについてはこちらで知識を学ぶといいでしょう。
「独学なんて面倒くさい」「きちんと専門家にみてもらいたい」という方は、co-nectがおすすめです。
co-nectは、肩や腰の痛みに対して、ストレッチや筋トレで根本的な体質改善を目的としたパーソナルジムです。
「怪我予防をしたい」「慢性的な痛みを治したい」と悩んでいる方におすすめです。



実際に行ってセッションを受けてみましたが、腰の調子がいい感じです
今なら初回体験50%オフ
怪我をしたくないあなたにおすすめ!
co-nectボディストレッチの評判、口コミってほんと?実際に行って体験したてみたら○○だった!通うべき人の特徴3選!
力任せなスパーリングをしない
初心者に多く見られがちなことですが、力任せにスパーリングをして怪我をするケースです。



格闘技を始めたばかりの頃は、力の抜きどころが分からず、不要な怪我をしました
怪我を予防するために、無駄な力を入れず、6、7割ぐらいの力で動くように意識しましょう。
それには基本的なムーヴができるようになることが重要です。
基本ができるようになったら、次はエスケープや基本なディフェンスを覚えましょう。
クラッシャーとの対戦は避ける
力任せに技をかけてくる人や体重差を無視して攻めてくる人など、危ない人達とのスパーリングも避けましょう。
こうした方達とスパーリングをしても、怪我をするだけです。



自分と同じぐらいの体格の方、黒帯や茶帯の上級者と練習しましょう
まとめ


柔術は怪我をしない競技なのか、解説してきました。
怪我の多い箇所は、以下の通りです。
怪我の比較的少ない競技です。
しかし、コンタクトスポーツである以上、怪我をするリスクはあります。
怪我をするリスクを踏まえた上で、怪我を予防することが大切です。
もし、柔術に興味を持って柔術ライフを送りましょう!
柔術に限らず、どんな競技でも怪我をするリスクはあります。
しかし、怪我予防をすることで怪我をするリスクは下げられます。
怪我を予防して、楽しい柔術ライフを送りましょう!
柔術に興味を持った方がいたら、以下の記事を参考にしてください



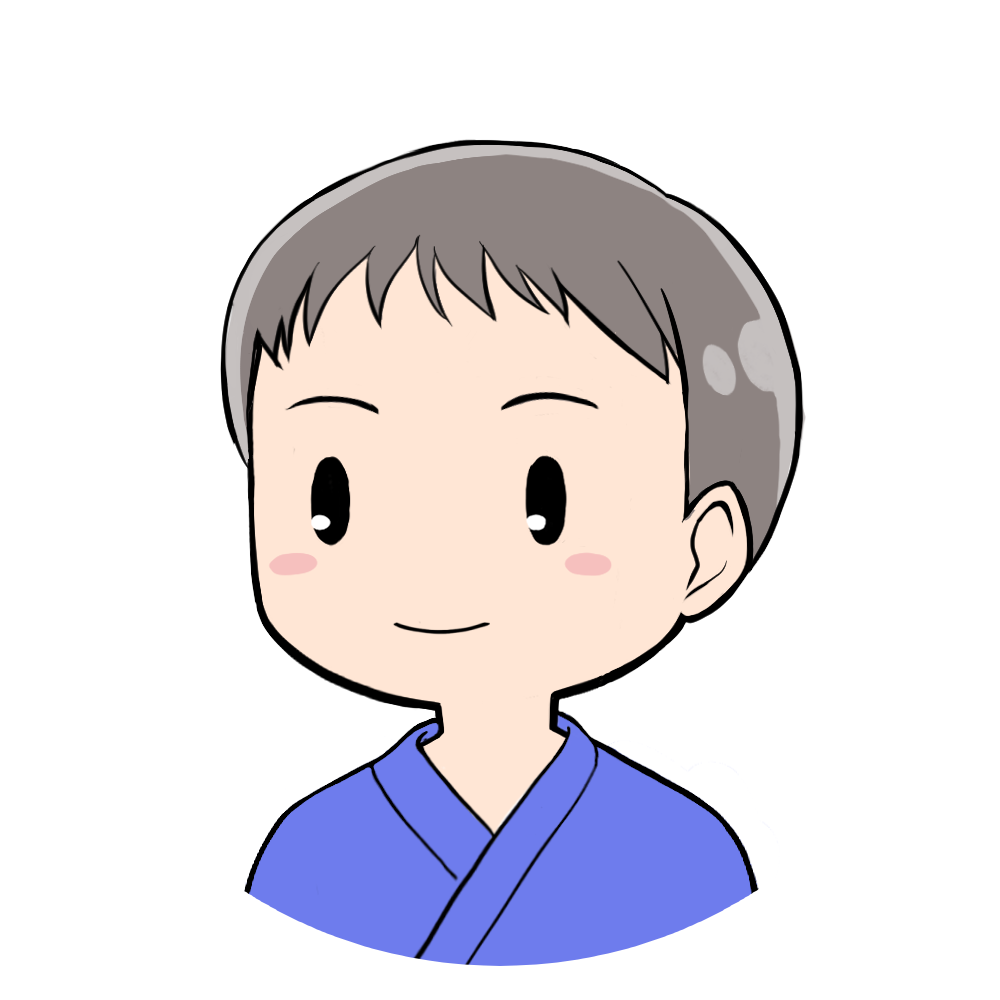

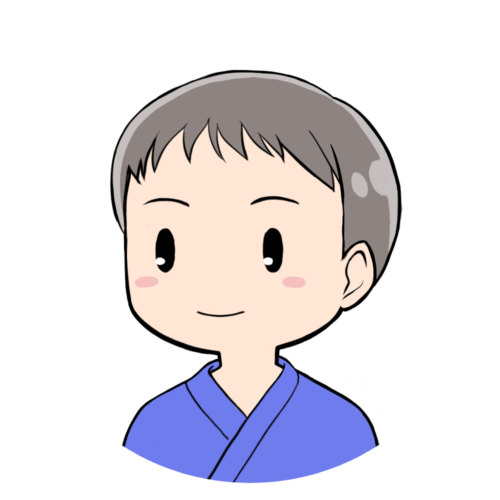






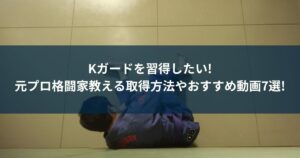




コメント